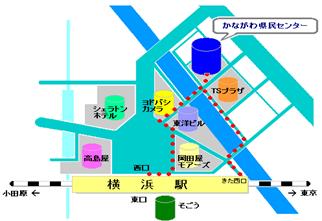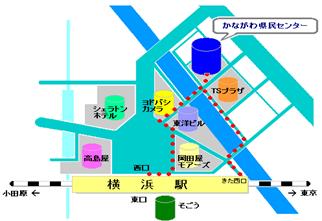「生」を肯定できない社会と教育の役割
稲葉 剛(NPO法人自立生活サポートセンター・もやい代表理事)
あるテレビ番組への反響から
今年5月、日本テレビの系列局で、私が代表理事を務めるNPO法人自立生活サポートセンター・もやいの活動を取材した『ネットカフェ難民3〜居場所どこに?』が放映されました。ネットカフェで生活せざるをえない若者たちの状況に象徴される、現代日本の貧困問題を早くから取り上げてきた水島宏明ディレクターによる一連のシリーズの最新作です。シリーズの3本目となる今作品では、サブタイトルに見られるように、経済的な困窮状態を経験した人々が回復していくために必要な「居場所」の問題に焦点が当てられており、<もやい>のもとに相談に来た十代の若者の状況と、彼らに付き添う<もやい>の若手スタッフとのやりとりが克明に描かれていました。
しかし、視聴者の反応は厳しいものでした。特に里親から見捨てられ、生活に困窮して路上生活を経験し、私たちの支援を受けて生活保護を受給することになった十代の若者に対して、「態度が悪い」とか、「あんな人に生活保護をかける必要は無い」といった内容の書き込みがインターネット上でなされ、テレビ局にも批判的な意見が多く届いたと聞いています。
特に、彼が金銭管理の重要性を説く<もやい>のスタッフに対して、「遊ぶお金が欲しい」とスタッフに迫る場面に非難が集中しました。「生活保護を受けていて、国のお世話になっているのに、『遊ぶお金が欲しい』とは何事だ?」というわけです。
私はこうした反応を見て、暗澹たる気持ちになりました。以前に比べて、貧困や格差に関する報道は増え、社会の中に理解が広がった面もありますが、やはり世間の主流は、「一生懸命がんばっている生活困窮者」なら同情するが、まだ「一生懸命がんばる」状態にまでなれないでいる者、彼のように大人から裏切られ続けて社会そのものが信じられなくなり、精神的にもつらい状態にいる若者の状況まではわかろうとしないのか、と思ったのです。
おそらく彼が、かつて私自身がそうであったように親の援助を受けて遊び暮らす学生であったのなら、そのことについてとやかく言う人はいなかったでしょう。しかし、家族からも児童福祉からも適切な援助を受けられなかった彼は、生活保護制度に頼って生きていかざるをえない。そして生活保護受給者となることで人々から厳しい監視の目を注がれる存在になってしまうのです。
「生」を無条件肯定できない社会
本来、憲法25条に明記され、生活保護法で具現化されている生存権は、誰であっても、どんな人であっても無条件に生きる基盤を保障する、という内容になっています。しかし、今の私たちの社会はまだそうした理念を受け入れる度量ができていないのではないのではないか。こういう「世間」の反応を見ると、まだ「生」が無条件に肯定される社会になっていない、という気がしてなりません。
よく生活保護受給者については、実際はごくわずかしかいない不正受給の問題が過剰に語られたり、「生活保護を受けているのに刺身を食べているのはけしからん」といったいわれのない批判がなされたりします。そしてそのような「世間の目」により、生活に困窮しても生活保護を受けることを躊躇したり、生活保護を受けていてもそれを隠して暮らさざるをえない人が大量に生み出されています。
私が感じるのは、そのように生活困窮者の暮らしをチェックして、他者が「生きる」ということに対してハードルを設けようとする人々は、実は自分自身の「生」も無条件に肯定していないのではないか、ということです。「一生懸命がんばっている」とか「働いて家族を養っている」とか、設定されるハードルはいろいろありますが、さまざまな不幸に見舞われて自分が設定したハードルを自分で乗り越えられなくなった時、自らの存在を肯定できずに苦しむのはその人たち自身ではないか、という気がしています。
今年10月に大阪で起こった個室ビデオ店放火事件も、生活保護を受けることを「恥ずかしい」と感じ、自分が生きることを肯定できずに心を病んでしまった男性が起こしてしまった事件でした。この事件が悲惨なのは、彼の「自傷行為」により巻き添えになり犠牲になった人々の多くもまた、生活に困窮し、個室ビデオ店やネットカフェなどで寝起きせざるをえなかった人々であった、ということです。
「経済的な貧困」と「人間関係の貧困」
私は、1994年から東京・新宿を中心に路上生活の人たちに関わり、路上の視点からこの社会が大きく移り変わっていくのを見てきました。バブル経済崩壊後、全国の大都市に現れた路上生活者を、行政を含め私たちの社会は基本的に放置してきました。路上や公園や河川敷に点在するダンボールハウスやブルーシートのテントは、90年代半ばから日常的な光景になり、そうした光景を見て育つ子どもたちに、「生活に困っても社会は手を差し伸べてくれない」、「だから、ああならないように頑張りなさい」という無言の「教育的効果」をもたらしました。
ここ数年は中高年の男性に限らず、「氷河期世代」を中心とする若年層にも貧困が広がり、「勝ち組・負け組」といった経済的な実力のみで人間を判定する浅薄な価値観が大手を振るようになりました。若者たちは、自らの経済的な価値をいかに向上させられるか、という競争に日々さらされることになります。
今年6月に東京・秋葉原で発生した無差別殺傷事件は、そうした社会の一つの帰結であるように私は感じました。「誰でもよかった」と言って人間のいのちを奪っていくことは決して許せることではありませんが、実は「誰でもいい」「代わりならいくらでもいる」と言われ続けてきたのは、あの事件を起こしたK容疑者自身だったのでないか。「生」を無条件に肯定することのできない社会で、「生きること」を肯定できなくなった者が他者を攻撃することで自分の生きている証を求めようとしたのではないか。そんな印象を持ちました。
K容疑者は、派遣社員として静岡県内にあるトヨタ系列の下請け工場で働いていましたが、ある日、出勤した際にツナギ(作業着)がなかったことがきっかけで「暴走」を始めたと言われています。ロッカーにツナギがなければ、同僚に聞いてみればいいのではないか、というのが健全な感覚ですが、彼にはそれができなかった。そこに派遣労働者の置かれている状況の特徴がある、と私は考えます。
その1つはその工場内でリストラが計画されているという噂があり、いつ仕事を失うかという不安に彼が怯えていたこと。もう1つは、工場に複数の派遣会社からバラバラに社員が派遣されていたため、名前で呼び合い、「同僚」と認め合えるような横の人間関係がそもそも存在しなかったと推測されることです。
貧困には「経済的な貧困」と「人間関係の貧困」という2つの側面がある、というのは、私たちが労働市場からはじき出された人々とふれあう中で気づいた観点ですが、近年では労働市場の中にまで「二重の貧困」が浸透している、ということを象徴するような事件でした。
このように、人間が取り替え可能な商品のように扱われる社会で失われるのは、個々の労働者の経済的な基盤だけでなく、自分自身が名前を持った一人の人間として尊重され、一対一の関係の中で他者とつながりあえるという感覚です。そして経済的にも困窮し、人間関係からも疎外された人々の中から、自分自身を傷つけたり他者への攻撃に走る人が出てきてしまうのです。
私たちの社会はついにこのような地点にまでたどり着いてしまった。では、市場原理至上主義的な価値観が蔓延する中で、一人ひとりの子どもを尊重し、子どもたちが自らの「生」を肯定しながら生きていける社会を作り直すために、教育に何ができるのか。一緒に考えていきたいと思います。